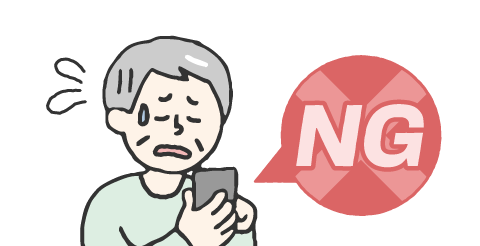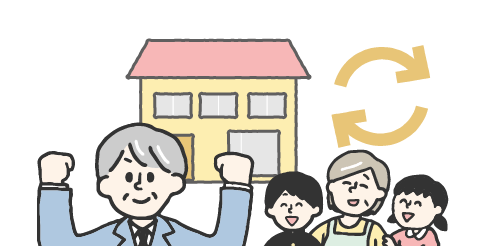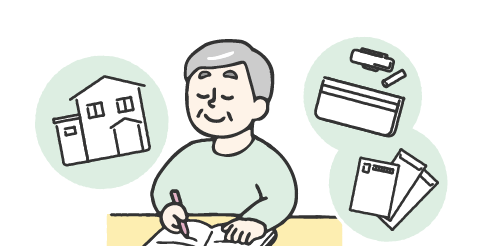リースバックがやばいと言われる理由は?
リースバックは、住宅を売却しつつ賃貸契約を結んで住み続けられる方法です。しかし、注意しなければ思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。この記事では、リースバックが「やばい」と言われる理由についてまとめました。
家賃が高かったり
値上げされてしまう
リースバック契約では、売却後に同じ家に住み続けられる利点がありますが、家賃が周辺相場よりも高く設定される場合があります。
また、契約時には予想していなかった家賃の値上げが発生することも少なくありません。これは、リースバック会社が物件の管理コストや将来的な市場の変動を考慮して、家賃改定の余地を契約に含めているためです。
家賃が高くなりすぎると、せっかくリースバックで住み続けることができても、家計に負担がかかり生活が維持できなくなる可能性があります。契約書に将来的な家賃の改定についての記載があるかどうか、事前にしっかり確認することが大切です。
自宅が売却されてしまう
リースバック契約では、物件の所有権がリースバック会社に移りますが、その後、業者が物件を第三者に転売するケースがあります。
転売が発生した場合、新しい所有者から契約条件の変更や、場合によっては退去を求められることがあり、住み続けられない、または買戻しができないリスクが生じます。
これを避けるためにも、契約時に転売の可能性や条件をしっかり確認しておきましょう。加えて、信頼できる業者を選ぶことが不可欠です。
修繕費用の負担が
あいまいにされてしまう
リースバック契約では、売却後も賃貸借契約に基づいて住み続けるため、家の維持費や修繕費用が発生します。
しかし、契約書内で修繕費用の負担がどちらにあるのかが明確にされていないケースがあります。そうなると、物件の大規模修繕が必要になった際に、思わぬ費用を請求されるかもしれません。
修繕費用に関する責任の所在は、契約書にしっかりと明記されているかを確認し、負担割合が不明確な場合は必ず質問しておきましょう。
退去を迫られる
リースバック契約を締結しても、何らかの理由で退去を求められるリスクはゼロではありません。
例えば、賃貸借契約の期限が来た際や賃料を滞納した場合などです。また、所有者が変わることで、賃貸契約が更新されずに退去を迫られる可能性も考えられます。
退去のリスクを避けるためには、契約書にある賃貸借契約の更新条件や解約条項を十分に確認し、安心感を持って住み続けられるかどうかを事前に確認することが必要です。
リースバックの
利用自体ができない
名義人全員の同意と売却価格の条件
リースバックを利用するには、まず名義人全員の同意が必要です。共同名義の物件では、全員の同意がないと契約は成立しません。
さらに、売却価格が住宅ローンの残債を上回ることも重要な条件です。物件の価値が低すぎてローンを完済できない場合、リースバックは利用できません。
家賃保証会社の審査
リースバック後、家賃を支払う能力を確認するために家賃保証会社の審査があります。この審査では、収入状況や信用情報がチェックされ、これに通らないと契約できません。
物件の状態と売却可能性
物件自体が売却可能な状態であることも条件です。権利関係が複雑な場合や物件に物理的な問題があると、リースバックが進まない、売却できないことがあります。
売却額の注意点
売却価格は市場価格の70%~90%であることが多く、相場より低めです。
また、リースバック後の家賃設定は売却価格の6%~13%程度が一般的で、この家賃が家計に与える影響も考慮する必要があります。契約書の内容もよく確認し、リスクやメリットをしっかり説明してくれる業者を選びましょう。
リースバックは
会社選びが重要
リースバックは、会社によって契約内容やサービスの質が大きく異なります。悪質な業者に依頼してしまうと、自宅の価格が相場より安く見積もられたり、不当な条件を押し付けられるリスクが高まります。そのため、リースバック会社選びは慎重に行いましょう。
信頼のある不動産会社を選ぶこと、また複数の会社から見積もりを取ることが、リースバックではとても大切です。
リースバックの契約書
リースバック契約では、主に売買契約書と賃貸契約書の2種類が使われます。それぞれの契約書に記載されるべき内容を十分に理解しておくことが、後々のトラブルを防ぐために重要です。
売買契約書
リースバックの売買契約書には、売主と買主の情報、売買物件の詳細、売買価格、手付金の額、そして物件の告知事項などを記載します。また、物件の決済期日や所有権の移転時期、税金の支払いについても詳細が書かれていることが一般的です。
契約書を確認する際は、売買価格が適正かどうか、物件に関する重要事項が正確に記載されているかを必ずチェックしましょう。特に、買戻しが可能かどうかや、その条件についての詳細を事前に確認しておくことが重要です。
賃貸契約書
リースバックで重要なもう1つの契約が賃貸借契約書です。賃貸借契約書には、賃貸借の種類(普通借家契約か定期借家契約か)、契約期間、家賃、敷金、礼金の金額、支払い方法の他、退去時に必要な原状回復や火災保険の加入義務について記載されています。
契約期間や退去時にどの範囲まで原状回復義務があるのかを理解しておくことが、トラブル回避につながります。
リースバックの契約書に
よくある特約
- 途中解約の特約
契約期間中に解約できるかは重要です。通常、リースバックでは中途解約が難しいため、解約権があるか、条件や違約金が記載されているかをチェックしましょう。手続き方法や退去時の対応も契約書でしっかり確認する必要があります。
- 買戻し特約
将来、自宅を再取得できるかの特約です。買戻し特約が含まれているか、期間や価格設定が明確かをチェックします。会社によって条件が異なるため、他社との比較検討が大切です。特約がない場合、買戻しの交渉が難しくなります。
- 禁止事項・ペナルティの特約
契約書には、入居者の行動に関する制約が設けられていることが多くあります。良くある制約には、ペットの飼育や無断転貸が禁止などがあり、違反すると罰則が適用されます。費用負担や契約解除など、ペナルティの条件も確認しましょう。
リースバック契約書の
チェックポイント
リースバック契約書を確認する際には、後々のトラブルを避けるために以下のポイントをチェックしておきましょう。
自分の住み続けたい
期間になっているか
契約書には契約期間と更新条件が明記されています。特に「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認し、再契約や更新の可否を把握しましょう。更新時の家賃改定や更新料もチェック箇所です。
また、定期借家契約の場合は、期間満了後の住み続けられる条件を明確にしておくことが重要です。
売買価格と家賃は適切か
契約書に記載された売買価格と家賃が適正かを確認するため、近隣の不動産価格や賃貸相場と比較しましょう。
また、家賃改定がある場合、その条件が明確に定められているかがポイントです。複数のリースバック会社から見積もりを取り、相場と照らし合わせて妥当な契約内容か判断してください。
買戻しは可能か
買戻し特約が契約に含まれているかの事項です。買戻しが可能な期間や価格設定が明確であるかをチェックし、いつまでにどの価格で買い戻せるかを把握しておきましょう。また、買戻し時の条件や手数料がかかるかどうかも重要なポイントです。
修繕の責任の所在はどこか
契約書内で、修繕費用の負担が誰にあるかを確認します。大規模な修繕(外壁や屋根など)はリースバック会社が負担するのが一般的ですが、日常的な修理や設備の故障は賃借人に負担がかかる場合があります。
また、退去時の原状回復費用の確認も、予想外の費用負担を避けるために見ておきたいポイントです。
まとめ
リースバックの契約では、問題視される点や注意点を事前に理解し、後々困らないようにすることが大切です。
特に、家賃や修繕費、契約期間など重要なポイントをしっかり確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。これらのリスクを加味しないと、「やばい」と言われる状況になる可能性があります。
このサイトでは、資金や現金化が必要になった状況別におすすめのリースバック会社を紹介しています。ご自身の状況と照らし合わせて相談をしてみてはいかがでしょうか。